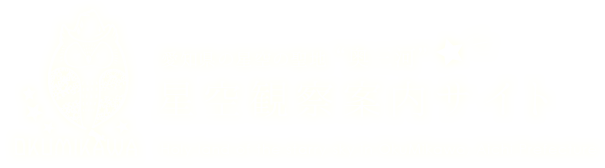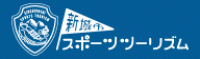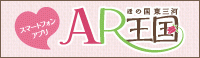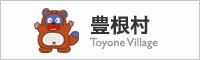惑星が見ごろです。
2025年の秋から冬にかけて、太陽系の惑星が見ごろを迎えます。
土星
宵空20時ころの東の空に、明るい星が目立って見えています。それは土星です。明るさは1等級。秋の星座、うお座に位置しており、まさに今が観望の好機です。
実は今年の土星は、とても珍しい見え方をしています。環が細くなっていて、まるで串団子、あるいは串というより針のように環が土星の本体に刺さっているように見えます。土星は約30年で太陽の周りを一周(公転)します。地球から見ると、約15年に一度、傾いた環を真横から見るタイミングが訪れますが、今年がまさにそのタイミングなのです。次に同じような見え方をするのは約14年後(2038年~2039年ころ)ですから、なかなかレアです。
11月24日ころ、地球がほぼ真横(完全に真横ではない)から環を見る、今回最後のタイミングが訪れます。ぜひ天文台や観察会で天体望遠鏡を使って観察してみてください。実は、環のない土星なんて「海苔のないおにぎり」のようなものですから、まず、環が見えているうちに環のある土星を観察しておくことをお勧めします。そして、環が隠れた時に「あ!環がない!」と気がつきましょう!
2年もすれば、環が開いて見えるようになります。「土星らしい環を観察したい!」という方は、毎年、観察して変化を感じてみるのも良いでしょう。
実は今年の土星は、とても珍しい見え方をしています。環が細くなっていて、まるで串団子、あるいは串というより針のように環が土星の本体に刺さっているように見えます。土星は約30年で太陽の周りを一周(公転)します。地球から見ると、約15年に一度、傾いた環を真横から見るタイミングが訪れますが、今年がまさにそのタイミングなのです。次に同じような見え方をするのは約14年後(2038年~2039年ころ)ですから、なかなかレアです。
11月24日ころ、地球がほぼ真横(完全に真横ではない)から環を見る、今回最後のタイミングが訪れます。ぜひ天文台や観察会で天体望遠鏡を使って観察してみてください。実は、環のない土星なんて「海苔のないおにぎり」のようなものですから、まず、環が見えているうちに環のある土星を観察しておくことをお勧めします。そして、環が隠れた時に「あ!環がない!」と気がつきましょう!
2年もすれば、環が開いて見えるようになります。「土星らしい環を観察したい!」という方は、毎年、観察して変化を感じてみるのも良いでしょう。


海王星
地球から約43億km。光の速さでも約4時間かかる距離にある、太陽系最遠の惑星「海王星」。明るさは8等星程度ですから、どんなに目を凝らしても肉眼では見えず、望遠鏡で探しても、まわりの恒星と区別がつきにくく、「ほんとうにこれかな?」という感想を抱くかもしれません。
しかし、今年は見かけ上、土星の近くに見えています。土星を望遠鏡の視野に入れてから、少し動かすと視野に入ってきます。その姿を見れば「間違いない。きっとこれだ!」と思えるでしょう。
よく観察すると、恒星とは違い、小さな円盤状で大きさ(視直径)があり、またたきません。色も少し青っぽく見えます。なかなか見るチャンスが少ない惑星ですので、この機会にぜひ天文台や観察会で天体望遠鏡で観察してみてください。
しかし、今年は見かけ上、土星の近くに見えています。土星を望遠鏡の視野に入れてから、少し動かすと視野に入ってきます。その姿を見れば「間違いない。きっとこれだ!」と思えるでしょう。
よく観察すると、恒星とは違い、小さな円盤状で大きさ(視直径)があり、またたきません。色も少し青っぽく見えます。なかなか見るチャンスが少ない惑星ですので、この機会にぜひ天文台や観察会で天体望遠鏡で観察してみてください。

天王星
土星の外側、海王星の一つ内側を回る惑星です。明るさは6等星ですから、非常に暗い夜空、例えば奥三河のような場所であれば肉眼で見える明るさではありますが、たくさんの星に紛れてしまうため探すのはなかなか難しいでしょう。
しかし、今年の天王星は、すばる(プレアデス星団 M45)の近くに見えており、望遠鏡なら探しやすい位置にあります。
秋の宵空ですばるが東の空に昇ってきたら、「この辺りに天王星がいるんだな」と感じてみてください。少し倍率を上げた望遠鏡で見れば、白く丸い円盤状に見えるはずです。これは、明らかに他の恒星とは違う見え方です。
しかし、今年の天王星は、すばる(プレアデス星団 M45)の近くに見えており、望遠鏡なら探しやすい位置にあります。
秋の宵空ですばるが東の空に昇ってきたら、「この辺りに天王星がいるんだな」と感じてみてください。少し倍率を上げた望遠鏡で見れば、白く丸い円盤状に見えるはずです。これは、明らかに他の恒星とは違う見え方です。

木星
太陽系で王者と称される、太陽系最大の惑星です。明るさはマイナス2等級に達し、11月には夜半前に東の空に昇ってきたふたご座の中でひときわ明るく見えるはずです。
明るい1等星がたくさんある冬の夜空にあって、ますます明るい木星。これからが本格的な観望の好機です。
少し倍率を上げた望遠鏡で、でっかい木星を観察してみましょう。春まで見えていますから、春の観察会でも十分に観察できるでしょう。
明るい1等星がたくさんある冬の夜空にあって、ますます明るい木星。これからが本格的な観望の好機です。
少し倍率を上げた望遠鏡で、でっかい木星を観察してみましょう。春まで見えていますから、春の観察会でも十分に観察できるでしょう。

現在、火星や金星、水星は太陽の近くに見えており、その観察がむずかしい時期です。
一方、太陽系外縁部からやってきている彗(すい)星があります。それはレモン彗星(C/2025 A6)です。この彗星は、米国アリゾナ州のレモン山天文台で発見されたことから「レモン」と名付けられています。
10月下旬から11月上旬にかけて、日の入り直後の西の空で、4等級程度の明るさになると予想されています。肉眼で見るのは難しいかもしれませんが、奥三河の観察会などで、望遠鏡や双眼鏡で観察したり、写真に撮ったりできるとよいですね。
こうしてみると、「さびしい」と言われる秋の夜空も実は結構にぎやかです。
奥三河では、毎週末のように天体望遠鏡を設置した星空観察会が開催されています。つぐ高原天文台でも、11月は金曜・土曜・日曜の夜に、一般の方も参加できる観察会を開催しています。ぜひ天体望遠鏡でこれらの惑星や彗星を観察してみましょう!
コラムby つぐ高原天文台・星空案内人 平野宗弘
(参考)